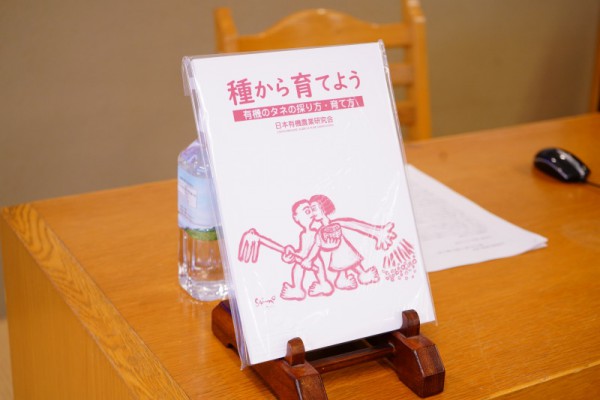本日7/6(水)、農業シンポジウムのアフターシンポジウムイベントとして、有機農業アドバイザーの林重孝(はやし・しげのり)さんによる講演「種から育てよう」が行われました。
千葉県佐倉市の2.4haの農地で約150品種を有機農業を行い、そのうち70品種ほどを自家採種をしながら栽培している林さんは、カルチャー教室などでも農業のテクニックを教える有機農業アドバイザーでもあります。 本日は、実際の栽培事例の豊富な画像を使った出張レッスンが行われました。
序盤で語られたのは「有機農業の普及に、種がいかに大切か」というお話。 日本の農業で使われる種苗の8割が海外から輸入される種。 そして、慣行農業を脱却できない大きな理由の一つに、現在多く売られる「品種の問題」があるそうです。
「長時間の輸送や、外食産業に好まれるように、段ボールに入れやすい中太りの大根や、かっぱ巻きの海苔のサイズに合わせた20~21cmのきゅうりなどに規格されてしまっている。また、化学肥料がたっぷりの土壌を前提として品種改良されているため、有機農業に向いた品種で育てる必要がある」
と、本来はそれぞれの固定種が持っていた個性が生かされていない現状を語ります。 慣行栽培にあわせて画一化されている種では、有機栽培では育てにくい現状があるのだそうです。 そこで林さんは、種取りからの有機栽培と母本選抜からの”好みの品種づくり”に励んでいます。
「手間がかかること、種とりまで圃場を占有してしまうので農地効率が悪くなるというデメリットもありますが、自分の好みの品種を作ることができる。種苗会社に依存して種を毎年購入しなくてよくなるため、農民の自立になります」 と話すのは自家採種の大切さ。
固定種を残していくために一番気をつけている「交雑」に配慮した繁殖の方法も、科目によって異なります。 講座では、作物ごとの種とりと繁殖のポイントも惜しみなく解説してくださいました。

休憩を挟んだ後半は「野菜づくりのコツ」として、微生物の多様性に富んだ林農園の土づくりのお話から。
やはり大切なのは土壌中の微生物相。
質のよい土を作るまでには10年ほどかかったといいますが、林農園の土は、市販の堆肥には見いだせないほど微生物活性が高く、アンモニア体窒素を硝酸体窒素に変化させてくれるので、植物が土壌から栄養を吸収しやすいのだそうです。
また、お互いの病気を防ぎあうコンパニオンプランツなど植物の持つ特性を生かした栽培方法、環境にやさしい防除法などが伝えられました。 有機農業は害虫がいないわけではありません。むしろ、害虫が出てくることで、それを食べる天敵(鳥やかえるなど)が現れるのです。
そうして生き物がどんどん増えてきて、生態系のバランスや生物多様性が整ってくるのだと林さんは語りました。 中には「病気で死んだヤトウムシをすり潰して水に一晩浸けたものを撒くと、特定の虫には100%効果が」という、同種療法ともいえる害虫対策も。
「有機とは何もしないことではありません。人間が手を加えて工夫しながら作物に合う環境を整えてあげること」と締めくくりました。
その後、会場からの質疑応答があり、堆肥づくりやベランダ栽培する際の土の手に入れ方などに、熱心なやりとりが交わされました。

▼▽書籍情報▽▼
林先生が副理事長を務める日本有機農業研究会から出版されている、有機農業の教科書「種から育てよう」は豊受モールにて販売しております。